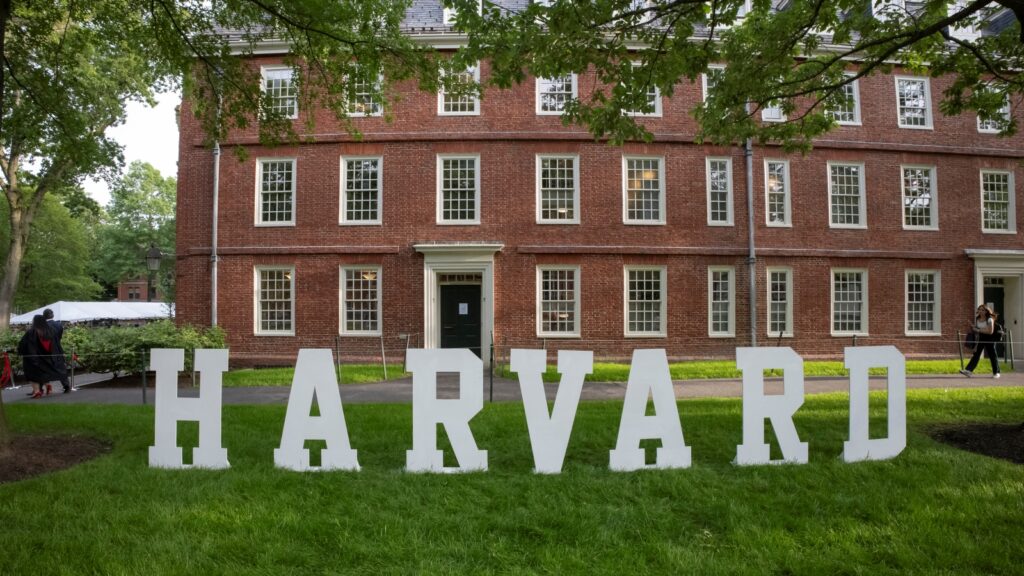トランプ大統領が就任して間もなく、米国内で物議を醸す大学との対立が表面化した。その大学とはハーバード大学である。批判の焦点は、同大学が米国の核心的価値観に反する行為に関与しつつ、米国内で得た資金や技術的優位性を利用して、中共による新疆での人権侵害、特にウイグル人に対するジェノサイドの助長に加担している点にある。
一般に、米国の大学教育は世界に誇る競争力の源泉であり、世界中の優秀な人材が目指す目標とされている。その中でも、米国最古の高等教育機関であるハーバード大学は、まさに「宝石」と称される存在だ。
しかし、他の多くのトップ大学と同様に、ハーバードは世界的な左派勢力の影響下にあり、結果として米国の戦略的敵対者である中共を間接的に支援しているとの批判も存在する。
米国務省の報告によれば、ハーバード大学を含む米国のトップ大学は、中共からの資金提供に一定程度依存しており、それがキャンパス内での事件対応にも影響を与えている。たとえば、反中共の抗議活動が無視されるケースなどが指摘されている。
また、ハーバード大学のケネディスクールは「中共の海外党校」と揶揄されることもある。その理由は、多くの中共高官やエリート層の子弟がここで教育を受けているためである。例えば、薄熙来の息子・薄瓜瓜は学業成績が平凡であったにもかかわらず入学を許され、習近平の娘・習明沢もかつて在籍していた。このような「赤い貴族(共産党高官など特権階級)」の子女がハーバードに進学できるのは、本当に学力や実力によるものなのか、疑問が呈されている。
さらに、中国学生学者連合会(CSSA)のハーバード支部は、中共の影響下にある代理組織と見なされており、キャンパス内で中共に反対する人々を監視し、攻撃する役割を果たしていると指摘されている。実際に、ある学生が中国の駐米大使による講演に抗議した際、この団体のメンバーから直接攻撃を受けた。
しかし、大学側は加害者に対して処罰を行わず、その行為を「理解できる」と表明した。この一件は、学問の自由やキャンパスにおける安全保障、そして大学運営における倫理的課題を浮き彫りにしている。
米国の大学におけるAIや科学分野のトップ研究者の約40%は中国出身であり、その多くが中共の「千人計画」を通じてリクルートされ、結果として技術流出のリスクが生じている。ハーバード大学もまた、中共の支配下にある教育機関と協力し、次世代の中共指導者の育成に関与していると指摘されている。
この動きは、学問や研究の名の下に行われる浸透行為と見なされている。今年の事例として、ハーバードは環境保護団体「中国生物多様性保護・グリーン発展基金会」に関係する中国人学生を卒業式のスピーカーに選出した。この基金会は中共と密接に結びついており、当該学生の父親も高級官僚である。
ハーバード大学の学生の約30%は外国人であり、コロンビア大学ではその比率が約40%に達する。米国のトップ大学は、政府から数十億ドルの研究補助金や税制優遇を受けつつ、米国人学生の受け入れ枠を減らし、対立する国家からの学生を優先的に受け入れているケースがある。
これに対して、トランプ政権はすでに反撃を開始し、連邦補助金の打ち切りを警告したり、コロンビア大学やブラウン大学などに罰金を科す措置をとった。しかし、こうした対応は十分とは言えない。
罰金はこれら大学にとって大きな痛手ではなく、大学側は「今後は繰り返さない」と曖昧な約束をするにとどまる。トランプ大統領が退任すれば、状況は再び元に戻る可能性が高い。
より有効な手段は、米国の大学に在籍する中国籍学生の数を大幅に削減することである。特に、AIや先端技術分野など、戦略的に重要な技術系学生の制限が急務だ。現在、米中はAI開発競争の最前線にあり、Meta(旧Facebook)のAI責任者である汪滔氏は「AIの進展速度を考えると、ライバルへの機密流出を防ぐために研究室をロックする必要がある」と指摘している。
しかし、現状では何千人もの中国人留学生がこれらの研究室で学び、研究に従事しており、技術流出のリスクは依然として高い。
昨年、米国は約110万人の国際学生を受け入れ、そのうち25%が中国人だった。さらに、2022年に米国で博士号を取得した科学系研究者のうち40%は外国籍であり、AI分野においては米国機関のトップ研究者の約40%が中国出身者である。中共は「千人計画」を通じて、米国で教育や勤務経験を積んだ研究者を積極的にリクルートし、自国の技術発展に活用している。
米国がイランのために核物理学者を育成したり、ロシアのために弾道ミサイル技術者を養成したりすることはないにもかかわらず、中共向けのAIや最先端技術の専門家育成には無頓着である。しかも、この問題はAI分野に限られず、あらゆる戦略的技術分野に広がっている。
米国の大学が中国人留学生を積極的に受け入れる理由は明白である。彼らは裕福で高額な学費を支払ううえ、中国系組織や企業からの研究資金をも大学にもたらすからだ。ゆえに、金銭的利益を優先する大学に対しては、罰金や補助金削減といった措置だけでは不十分である。
最も直接的かつ効果的な対策は、ビザ発給の制限である。これは連邦政府が持つ固有の権限であり、具体的には、中共党員やその子弟への学生ビザ発給の停止、中共軍の兵器開発との関係が深いとされる「国防七校」関係者の入国拒否、さらには中国人研究者による米国国立研究所への立ち入り禁止などが求められる。
反対意見として、「学術交流のためには中国人学生の受け入れが不可欠であり、文化交流を通じて自由や民主主義の価値が中国に普及する」という主張がある。しかし、それは理想的な建前にすぎず、現実の中国とは一致していないと指摘もある。
実際に、中共序列第4位の王滬寧はかつてミシガン大学やカリフォルニア大学バークレー校に留学したが、その経験を経てむしろ強硬な思想を深めたとされる。また、ハーバード大学で学び「西側の箔」を得た中共党員たちが、帰国後に中国の民主化を推し進めた例はほとんど存在しない。むしろ逆に、米国の側こそが学術の名を借りた浸透と価値観の変質という被害を受けているのである。