中国恒大と不動産管理部門、香港市場で取引停止-理由は不明
原題:Evergrande, Property Management Unit Share Trading Halted (1)(抜粋)
(c)2021 Bloomberg L.P.
Russell Ward



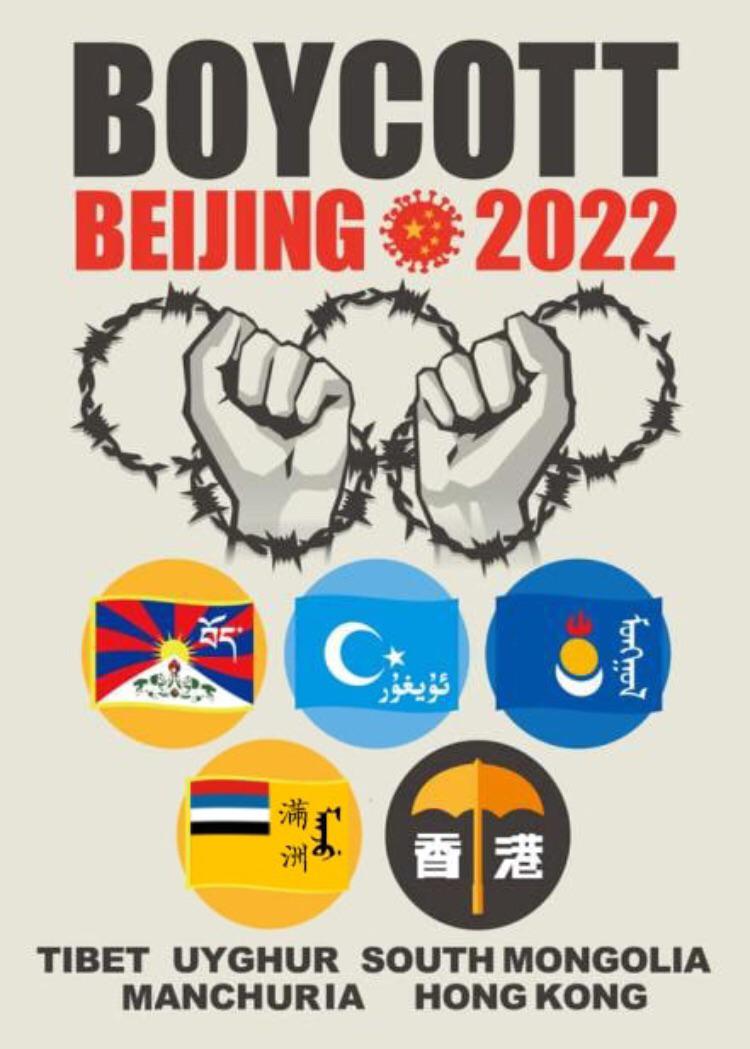
中国恒大は前座!後に控えるリーマン級危機に世界は対処できるのか
中国恒大は氷山の一角

by Gettyimages
中国恒大問題については、10月2日公開の「これは習近平の経済自爆戦術か、行き着く先は巨大な北朝鮮」や9月29日公開「習近平が目指すのは朝貢貿易か? 中国TPP加盟という暴挙を認めるな」4ページなどで、たびたび触れてきた。 【写真】恒大危機など序の口、中国不動産バブルの恐るべき深度と規模の全体像 本稿執筆時点では、まだ9月23日に実行すべきであった利払いの猶予期間である30日が経過していないので断定はできないが、債務不履行になる公算が高いと考える。前記記事で述べたように、習近平氏は、「わざと中国経済を崩壊させて、世界貿易などを通じて他の国に「(経済)破綻ミサイル攻撃」」を行おうとしているのではないかと考えるからだ。 しかし、私の見立てが杞憂であって、「習近平政権は全力で中国経済の崩壊を食い止めようとしている」場合でも、結局結果は同じであると考える。 問題は中国恒大だけにあるのではない。日本の1980年代バブル期と同じように、ほとんどの中国の不動産会社が身の丈に合わない事業拡大をおこなっており、それらの企業群の危機も控えているから、中国恒大だけを救済しても焼け石に水に過ぎないのだ。 天を覆いつくす風船のように膨れ上がった中国の不動産業界全体を救済することなど到底不可能であり、たとえ習近平政権がバブル崩壊を恐れているにしても、救済せずに「秩序ある崩壊」に導くしかないと言える。 だが、政府があの手この手で「秩序ある崩壊」を実行することなど簡単ではない。しかも、市場原理を無視し「毛沢東路線回帰」を鮮明にしたうえで、「経済よりもイデオロギー優先」の習近平政権が、そのような高度な技を披露できるはずもない。 さらに、中国恒大集団傘下でEVの開発・生産を手掛ける中国恒大新能源汽車集団は、9月24日、迅速な資金注入がなければ資金繰りが破綻すると発表した。この自動車会社は、EVブームに乗っただけの(実質的な機能が無い)単なる「見せかけの箱」とも評される。 それにも関わらず、今年の春には米国フォード・モーターの時価総額を抜いていたとも伝えられるのだ。 不動産だけではなく、あらゆる分野のバブルが崩壊しつつあるのが、共産主義中国の実態である。 また、中国当局が暗号資産(仮想通貨)に関連する全ての取引と採掘(マイニング)を禁止すると発表している。この理由については、色々と論評されているが、真の狙いは「人民元(国内資金)の持ち出しをストップさせる」ことにあるのではないだろうか? 「上に政策あれば下に対策あり」が中国の伝統だ。民間企業たたき、外資系いじめ、さらには「経済崩壊黙認」の習近平氏の「政策」に対して、庶民が「国外への資金持ち出し」という「対策」をかなり積極的に進めているのだと考える。 また、中国恒大の米ドル建て社債の利払いが行われていないのは、実は公式統計では潤沢にあるはずの(米ドル)外貨準備が、(巷でうわさされるように)枯渇しているからなのかもしれない。 中国恒大問題は、中国経済崩壊を知らせる「坑道のカナリア」のような気がする。
中国恒大は何匹目のゴキブリか?
4月20日公開「『ドルが紙くずになるかもしれない』時代に考えるべき、これからの金の価値」で、アルケゴスやグリーンシルの問題に触れたのは半年ほど前のことだが、その後日本や世界で余りにも色々な事件が起っているので、読者はもう忘れていたかもしれない。 だが、世界経済に対して半年前に、カナリアが親切にも我々に危険を教えてくれていたのである。 昨年3月29日公開「バフェットの師匠が教える『粉飾決算の見分け方』」、同7月15日公開「ワイヤーカード・スキャンダルは実はエンロン事件並みの衝撃かも」8ページ「ゴキブリが1匹だけのはずがない」などで述べたように、投資の神様バフェットは、「1匹目のゴキブリ」を見つけた時に対処すべきだと述べている。 ゴキブリが目の前の1匹だけではなく、流しの奥の配管の陰に巨大な巣をつくっていると考えるべきなのだ。そして、今回の恒大問題を見ると、やはり「ゴキブリは1匹だけではなかった」ということである。 グリーンシル、アルケゴス、さらにはワイヤーカード以外にも、すくなからぬ数の「ゴキブリ」がこれまで目撃されており、中国恒大が最初のゴキブリというわけではない。したがって、配管の裏から「ゴキブリの大群」がそれほど遠くない将来にやってくる可能性が高いように思える。
いつ目の前に現れるのか?
問題は、いつ「ゴキブリの大群」が我々の目の前に登場するのかということである。それが「明日」である可能性は否定できないが、バブル崩壊のパターンを振り返って見ると、アルケゴス、グリーンシルや中国恒大のようなはっきりしたサインが出ているのに「それはそれ、市場全体に影響はないさ!」という楽観論が支配的であることが多い。したがって、事の重大性に比較して、市場は堅調に推移するわけだ。 「見たくないものはできるだけ見ないようにする」人間心理がそのような行動をとらせるのであろうが、遅かれ早かれ「真の姿」を直視することを迫られる。 そのある一定の瞬間に「オセロの盤面が白から黒に変わる」ように、「強気」が一瞬で「弱気」に変わるのが過去のバブル崩壊の典型だ。 「事実」よりも「人間心理」の与える影響が大きいから、行動経済学的に考えるべきだが、「人間心理の変化」を合理的に言い当てるのは難しい。だから、バフェットが述べるように「常に危機に備えるべき」だ。そして、現在は南の島で台風が発生した段階ではなく、日本本土のど真ん中を直撃するコースを驀進している段階といえよう。 「台風が我が家を直撃する」と考えて備えるべきだ。
サブプライム危機後のリーマンショック
今回の中国恒大問題が、リーマンショックのような事態につながるのではないかという話が出ているが、私はむしろサブプライム危機と比較するべきではないかと思う。 サブプライム(住宅ローン)危機とは、2007年末から2009年頃を中心として米国で起きた、住宅購入用途向けサブプライム・ローンの不良債権化のことをさすが、この問題が表面化した2007年頃から株式市場にもかなりの影響があった。 しかし、世界経済・市場に超ド級の影響を与えたのは、翌年、2008年秋のリーマンショックであることは読者も周知の通りである。 恒大問題も、「過剰な借金によって不動産を購入して値上がりを待つパターンの崩壊」という点ではサブプライム危機に近い。 たぶんこれから、中国の不動産市場を中心とした混乱が長引くであろうが、実はそれが前座でしかないのではないかと恐れている。 引き金は中国の不動産市場ではあるが、数か月から1~2年の間に欧米でも次々と新たな問題が噴出して、おおよそ1世紀ぶりに「世界大恐慌クラス」の大激震が世界にはしる可能性を否定できないと思う。
1929年株式大暴落は当時の新興国米国から始まった
私が不気味な一致だと考えているのは、世界大恐慌の震源地であり、1929年にNY株式市場大暴落を経験した米国が、当時の「巨大な新興国」であったことだ。 第1次世界大戦で自国の(国土の)被害が無かった米国は、国土が荒れ果てた英仏などの戦勝国に多額の貸し付けを行っていた。ドイツが巨額の賠償金を背負わされたことがナチス台頭の原因となったことは良く知られているが、フランスなどがドイツに巨額の賠償金を要求したのは、彼らが米国に多額の借金をしており返済しなければならなかったからだ。 欧州の没落を横目に米国だけが我が世の春を謳歌していたのだが、それが1929年に突然終わった。それだけではなく、その余波は世界中に広がって、第2次世界大戦が終結するまで世界はその影響から逃れることが出来なかった。 「恒大ショック」がどのように厳しいものであっても、「世界恐慌」につながらなければ恩の字だ。これまで我々が経験してきたリーマンショックなどのおおよそ10年ごとの危機と同様に、数年以内には立ち直るであろう。 だが、「世界恐慌クラス」の激震となれば、少なくとも10年、場合によっては20年も30年も我々は苦しめられることになる。 1929年当時の米国同様、強大な新興国・中国の経済的破綻が世界に与える惨劇は巨大なものになるかもしれない
13年もたっている
「世界恐慌」は、最悪のシナリオとして、概ね10年ごとに起こってきた世界的金融危機が13年間起こっていないのは事実だ。 2021年初頭からのパンデミックによるバラマキが下支えしたともいえる。 9月16日公開「東大寺の大仏を建立した『厄病退散』文化復活でコロナ禍を乗り切れ」で述べたように、おおよそ3年でパンデミックが沈静化した時の方が恐ろしいかもしれない。 私が「次にやってくる危機」に身構えているのは、世界的に超低金利政策やパンデミック対策のバラマキが派手に行われたおかげで、「金融緩和」という「伝家の宝刀」を抜くのが難しくなっているからである。以前から述べていることだが、政府や金融当局は一体どのような手段で危機に立ち向かおうというのだろうか? 最近、「リーマンショック型」なのか「LTCM型」なのかという議論がなされる。 LTCMとは、1997年に発生したアジア通貨危機とその煽りを受けて1998年に発生したロシア財政危機などによって瀬戸際に立った、ノーベル経済学賞受賞者なども参加したファンドである。 この危機の際に、FRB議長アラン・グリーンスパンは、FF(短期金利)レートを1998年9月からの3ヵ月間で3回引き下げるという急速な対応をとり、拡大した金融不安の沈静化を図っている。 しかし、現在の超低金利環境では利下げの効果がほとんど期待できないし、そもそも恒大危機の本質は「1社だけの問題ではない」というのが私の見立てである。 結局、どのように転んでも「大型の危機はやってくる」と考えるべきだ。明日なのか、1~2年後なのかはわからないが、我々は雨戸を閉め、庭に放置された道具などを片付けて大型台風に備える時期に来ているということである。
大原 浩(国際投資アナリスト)
